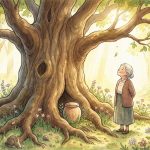「この先、もし自分に何かあったら、誰が気づいてくれるんだろう…」
「たくさんの手続きや片付けは、一体誰に頼めばいいの?」
おひとりさまで暮らしていると、ふとした瞬間にこんな不安が胸をよぎることがありませんか。
こんにちは、終活カウンセラーの鈴木由美子です。
何を隠そう、私自身が3年前に夫を突然亡くし、真の意味での「おひとりさま」になった一人です。
それまで夫に頼りきりだった私は、葬儀の手配から無数の手続き、そして跡継ぎのいないお墓の問題まで、すべてを一人で決断しなくてはなりませんでした。
その時の心細さ、途方に暮れる気持ちは、今でも忘れられません。
そんな孤独と不安の真っ只中にいた私を支えてくれたのが、一冊の「エンディングノート」でした。
自分のことを書き出し、想いを整理していく作業は、まるで未来の自分と対話するようでした。
それは、「一人でも大丈夫」という確かな安心感を与えてくれたのです。
この記事では、私の実体験と終活カウンセラーとしての知識を元に、おひとりさまのあなたにこそ書いてほしいエンディングノートの書き方をお伝えします。
これは決して「死ぬための準備」ではありません。
これからの人生を、あなたらしく、安心して、前向きに生きていくための、最初の素晴らしい一歩なのです。
目次
エンディングノートとは何か?
エンディングノートという言葉は聞いたことがあっても、具体的にどんなものか、遺言書とどう違うのか、はっきりと分からない方もいらっしゃるかもしれませんね。
まずは基本から、ゆっくり見ていきましょう。
エンディングノートの基本的な役割
エンディングノートは、ひと言でいえば「もしもの時に備えて、自分の情報や希望を書き留めておくノート」のことです。
元気なうちに、自分の人生の棚卸しをしながら、大切な情報をまとめておく、いわば「未来の自分からの引継ぎ書」のようなものです。
残された家族や友人が手続きなどで困らないように、という目的もありますが、それだけではありません。
書くことを通じて自分の人生を振り返り、これからの生き方を見つめ直すきっかけにもなる、とてもパーソナルな記録なのです。
遺言書との違いと使い分け
「エンディングノートと遺言書って、何が違うの?」これは本当によく聞かれる質問です。
一番大きな違いは「法的な効力があるかどうか」です。
| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |
|---|---|---|
| 法的効力 | なし(希望を伝えるもの) | あり(法的に実現できる) |
| 書式 | 自由(市販品、自作ノートなど) | 法律で定められた形式のみ有効 |
| 内容 | 自由(情報、希望、想いなど) | 主に財産分与や子どもの認知など |
| 作成時期 | いつでも | 一般的に15歳以上 |
| 開封時期 | いつでも | 本人の死後 |
このように、役割が全く異なります。
例えば、財産の分け方など法的に実現させたいことは「遺言書」に書く必要があります。
一方で、「お葬式はこぢんまりと、好きだったお花を飾ってほしい」といった希望や、友人への感謝のメッセージなどを伝えるのは「エンディングノート」の得意分野です。
両方の良いところを理解して、上手に使い分けるのが賢い方法ですね。
「おひとりさま」にとっての特別な意味
家族がいる方にとっても大切なエンディングノートですが、私たち「おひとりさま」にとっては、さらに特別な意味を持つと私は感じています。
それは、自分の代わりに想いや情報を伝えてくれる、唯一無二の「代弁者」になってくれるからです。
倒れた時に誰に連絡してほしいのか。
どんな医療を受けたいのか。
大切にしているペットの世話はどうするのか。
こうした情報を書き記しておくことで、万が一の時、あなたの意思が尊重され、周囲の人の負担も大きく減らすことができます。
それは、孤独な戦いを支えてくれる、心強いサポーターでもあるのです。
書き始める前に:心と環境の準備
「さあ、書こう!」と思っても、いざノートを前にすると、何から書けばいいのか手が止まってしまうかもしれません。
大丈夫、焦る必要はありません。
まずは、書くための心と環境を整えることから始めましょう。
書くことで向き合う「孤独」と「希望」
エンディングノートを書くことは、自分の「もしも」や「死」について考えることでもあります。
特に一人でいると、その作業が孤独感を深めてしまうように感じるかもしれません。
私も最初はそうでした。
夫のいない現実、一人で最期を迎えるかもしれない未来を想像して、胸が苦しくなりました。
でも、書き進めるうちに気づいたのです。
これは、漠然とした不安を「具体的な準備」に変える作業なのだと。
不安の正体が分かれば、対策ができます。
それは、暗闇の中に、自分で希望の光を灯していくような作業でした。
気持ちの整理に役立つノートとの付き合い方
エンディングノートは、誰かに提出する宿題ではありません。
完璧を目指さなくて大丈夫です。
- 書きたくない項目は、今は飛ばしてOK
- 気持ちが乗らない日は、無理に書かない
- まずは、楽しい思い出や好きなことリストから書いてみる
こんな風に、気楽に付き合ってみてください。
大切なのは、あなた自身の気持ちに正直であることです。
お気に入りのノートとペンを用意したり、好きな音楽を聴きながら書いたりするのも、気持ちを前向きにしてくれる素敵な工夫ですよ。
書き出すタイミングと心構え
「いつから書けばいいですか?」と聞かれることも多いですが、答えは「思い立ったが吉日」です。
ただ、心や時間に余裕がある時の方が、落ち着いて自分と向き合えます。
例えば、こんなタイミングはいかがでしょうか。
- 誕生日や新年など、節目を迎えた時
- 少し時間ができた休日
- 友人や知人の「もしも」の話を聞いた時
大切なのは、「終活=縁起でもない」と考えるのではなく、「これからの人生をより良く生きるための準備」と捉えることです。
そう思うだけで、不思議と前向きな気持ちでペンを取れるはずです。
書くべき内容とそのポイント
では、具体的にどんなことを書けば良いのでしょうか。
ここでは、おひとりさまにとって特に重要だと私が感じている項目を、ポイントと共にご紹介します。
1. 自分の基本情報と連絡先リスト
これは最も基本であり、最も重要な部分です。
氏名、生年月日、住所、本籍地、マイナンバーなどの基本情報を正確に記しましょう。
そして、「もしもの時に連絡してほしい人」のリストは必ず作成してください。
親族だけでなく、親しい友人、かかりつけ医、お世話になっている専門家(税理士など)の連絡先も忘れずに。
2. 医療・介護の希望(延命措置・施設選びなど)
自分の意思を伝えられなくなった時のために、医療や介護に関する希望は明確にしておきましょう。
- 延命措置は希望するか、しないか
- 意識がなくなった時の告知を誰にしてほしいか
- 介護が必要になったら、自宅で過ごしたいか、施設に入りたいか
- 希望する施設の種類や予算
夫が倒れた時、本人の希望が分からず、私は本当に悩みました。
あなたの希望を書いておくことが、周りの人の精神的な負担を軽くすることにも繋がるのです。
3. 財産と相続について(預貯金・保険・遺言の有無)
お金の話は書きにくいかもしれませんが、とても大切です。
- 預貯金(銀行名、支店名、口座番号)
- 生命保険、医療保険(会社名、証券番号)
- 不動産や有価証券の情報
- 借入金やローン
- 遺言書の有無と保管場所
通帳や証券のありかを記しておくだけで、手続きが格段にスムーズになります。
4. お葬式とお墓の希望(永代供養・樹木葬など)
跡継ぎのいない私たちにとって、お葬式やお墓の問題は切実です。
「誰にも迷惑をかけたくない」という気持ちが強いからこそ、自分の希望をはっきりと示しておくことが大切です。
- お葬式の規模や形式(家族葬、直葬など)
- 宗教・宗派についての希望
- 遺影に使ってほしい写真
- お墓の希望(永代供養墓、樹木葬、散骨、手元供養など)
私も、夫亡き後のお墓をどうするかで悩み、最終的には管理の負担がない永代供養付きの樹木葬を選びました。
色々な選択肢があるので、元気なうちに情報収集しておくと安心です。
最近では、お墓を新しく建てることだけでなく、既存のお墓への戒名彫りといった細かな相談にも親身に応じてくれる、地域に根差した専門家もいます。
例えば、熊本市の信頼できる石材店では、お墓に関する様々な相談や見積もりに無料で応じてくれるところもあるようですので、まずは地元の専門家に話を聞いてみることから始めるのも良いでしょう
5. デジタル遺品の整理(パスワード・SNSなど)
現代ならではの項目ですが、非常に重要です。
スマートフォンやパソコンのパスワードが分からないと、誰も中を見ることができません。
- スマホ、PCのログインパスワード
- よく利用するサイトのIDとパスワード
- SNSアカウント(Facebook, X, Instagramなど)をどうしてほしいか
- ネット銀行やネット証券の情報
パスワードをノートに直接書くのが不安な場合は、「ヒント」を書いておくだけでも良いでしょう。
6. 大切な人へのメッセージ
エンディングノートは、事務的な情報の引継ぎだけではありません。
あなたの素直な気持ちを伝える、最後の手紙にもなります。
これまでお世話になった友人や、遠くに住む親戚へ。
言葉ではなかなか伝えられなかった感謝の気持ちを、ぜひ書き残してください。
そのメッセージは、残された人の心を温め、悲しみを乗り越える力になるはずです。
書き方のコツと継続の工夫
いざ書き始めても、続けるのが難しいと感じるかもしれません。
ここでは、私が実際に試してみて良かった、ちょっとしたコツをご紹介しますね。
私が実際に書いて気づいたポイント
エンディングノートは、一度書いたら終わりではありません。
状況や気持ちは変わっていくものですから、いつでも書き直せるようにしておくのがおすすめです。
- 鉛筆やフリクションペンで書く: 間違えても気軽に消して修正できます。
- 付箋を活用する: まだ確定していないことや、考え中のことは付箋に書いて貼っておくと便利です。
- ルーズリーフやバインダー形式にする: ページの追加や入れ替えが自由にできて、とても管理しやすいです。
一気に完成させなくて大丈夫
「全部埋めなきゃ」と気負うと、疲れてしまいます。
「今月は財産のことだけ」「今日は連絡先リストを更新しよう」というように、テーマを絞って少しずつ進めるのが継続のコツです。
1年に1回、自分の誕生月に見直す、などとルールを決めるのも良い方法ですよ。
書き直しや更新のしやすい方法
最近では、パソコンやスマートフォンで作成できるデジタルのエンディングノートもあります。
修正が簡単で、情報を整理しやすいのがメリットです。
ただ、パスワードが分からないと誰も見られないというデメリットもあるので、紙のノートと併用するのが一番安心かもしれませんね。
紛失しない保管方法と見つけてもらう工夫
せっかく書いたノートも、見つけてもらえなければ意味がありません。
かといって、誰でも見える場所に置いておくのも心配ですよね。
「エンディングノートは、金庫にしまってはいけません」
これは、私が終活カウンセラーの勉強で教わった言葉です。
銀行の貸金庫などは、本人の死後、手続きが非常に煩雑で、すぐには開けられないことが多いからです。
おすすめは、本棚や引き出しなど、普段から使っているけれど少しプライベートな場所です。
そして何より大切なのは、信頼できる友人や親族、専門家などに「エンディングノートを書いてあること」と「その保管場所」を伝えておくことです。これが一番確実な方法です。
一人でもできる安心準備のステップ
「周りに頼れる人が本当にいない場合はどうすれば…」
その不安、痛いほどよく分かります。
でも、大丈夫。一人でもできる準備はたくさんありますし、私たちを支えてくれる社会の仕組みも存在します。
終活カウンセラーとしての具体的アドバイス
まずは、エンディングノートを書くことから始めてみましょう。
それが、あなたの不安を整理し、次に行うべきことを明確にしてくれます。
ノートを書きながら、分からないことや不安なことが出てきたら、それをリストアップしておきましょう。
そのリストが、専門家に相談する際の道しるべになります。
役立つツール・資料・サービスの紹介
今は、おひとりさまの終活をサポートしてくれる便利なものがたくさんあります。
- 市販のエンディングノート: 書くべき項目が網羅されていて、初心者でも取り組みやすいです。
- 自治体のパンフレット: 終活に関する情報や相談窓口をまとめた冊子を配布している市町村も増えています。
- 身元保証サービス: 入院時の身元保証人や、死後の事務手続きを代行してくれる民間のサービスもあります。
周囲に頼れる人がいない場合の対処法
もし、ノートの存在を伝えたり、いざという時を託せる人が身近にいなくても、諦めないでください。
公的なサポートを頼るという、大切な選択肢があります。
地域包括支援センターや成年後見制度の活用
少し難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、これらは私たちおひとりさまの強い味方です。
- 地域包括支援センター:
高齢者の暮らしを支えるための総合相談窓口で、全国の市町村に設置されています。保健師や社会福祉士などの専門家が、無料で相談に乗ってくれます。介護や健康、生活の困りごとなど、何でも相談できる「よろず相談所」と覚えておいてください。 - 成年後見制度:
認知症などで判断能力が不十分になった時に、あなたの代わりに財産管理や契約手続きを行ってくれる人を法的に定める制度です。元気なうちに、自分で信頼できる後見人を選んでおく「任意後見」という仕組みもあります。
こうした制度があることを知っておくだけで、将来への不安が少し和らぎませんか?
書いた後に感じた心の変化
私自身、エンディングノートを書き終えた時、そして今も時々見返して更新する中で、心に大きな変化がありました。
「自分の人生を自分で整える」ことの大切さ
夫に頼りきりだった私が、自分の力で、自分の最期までを見据えて準備をする。
その行為は、私に「自分の人生の主役は、他の誰でもない自分自身なのだ」という自信を取り戻させてくれました。
誰かに迷惑をかけたくない、という気持ちから始めた終活が、いつしか自分の人生を慈しみ、最後まで自分らしくありたいという前向きな気持ちに変わっていったのです。
書くことで不安が軽くなる
「もし私が倒れたら…」
「お金のことはどうなるんだろう…」書く前の私は、漠然とした不安の霧の中にいました。
でも、ノートに一つひとつ書き出していくことで、霧が晴れていくように感じたのです。
不安は「やるべきこと」に変わり、何をすればいいかが見えてきました。
一人でも前を向ける実感
エンディングノートを書き終えた今、私は「おひとりさま」であることに、以前のような孤独や恐怖を感じていません。
もちろん、寂しい時もあります。
でも、自分で未来への準備をしたという事実が、私を強くしてくれました。
終活は、決して後ろ向きな活動ではありません。
残りの人生を、どう楽しく、自分らしく、安心して生きていくか。
それを考える、最高に前向きな作業なのです。
まとめ
エンディングノートは、私たち「おひとりさま」の終活における、本当に強い味方です。
その一冊が、あなたの代わりに想いを伝え、もしもの時の手続きを助け、そして何より、あなたの心を軽くしてくれます。
- エンディングノートは、未来の自分からの「引継ぎ書」であり、おひとりさまの「代弁者」です。
- 完璧を目指さず、書けるところから、自分のペースで書くことが大切です。
- 医療や介護の希望、財産、お墓のことなど、具体的な希望を記しておきましょう。
- 頼れる人がいなくても、地域包括支援センターなどの公的なサポートがあります。
- 書くことは、過去と向き合い、未来を整える、前向きな行為です。
この記事を読んで、「少し書いてみようかな」と思っていただけたら、これほど嬉しいことはありません。
大丈夫。あなたは一人じゃありません。
私も、同じ道を歩む仲間として、あなたを応援しています。
あなたの人生が、あなたらしく、最後まで豊かに輝くことを心から願っています。